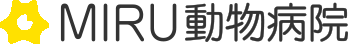新着情報NEWS
助けて!うちの猫が苦しそう!
こんにちは、獣医師の道本です。
9月に入り、少しずつ秋の気配が感じられるようになってきましたね。まだまだ残暑厳しいですが、朝晩が涼しくなって皆様の猫ちゃんも過ごしやすくなっているではないでしょうか。
『最近、うちの猫、呼吸が速くて元気がない気がする』
日々の診察の中でそんなご相談を受けることがあります。
このようなご相談から、検査を進めていく中で、循環器疾患、呼吸器疾患、内分泌疾患、整形外科疾患など様々な病気が見つかることがあります。今回はその中でも、皆様の大切な猫ちゃんたちに関わる「肥大型心筋症」という病気についてお話ししたいと思います。様々な循環器疾患がありますが、特に猫ちゃんでは比較的発生頻度が高い病気となります。猫ちゃんを飼っている方には、ぜひ知っておいてほしいことです。
※少し長めの内容となるため、要点だけ抑えたいという方は、最後の「肥大型心筋症かもと言われた…どうする?」の☆からだけでも読んでいただけると幸いです。
◯肥大型心筋症って何?
肥大型心筋症(ひだいがたしんきんしょう)は、猫の心臓の病気の一つで、心筋が厚くなってしまう状態を指します。肥大型心筋症の猫ちゃんの心臓では、心筋自体の肥厚・線維化や心筋配列の変化から、心室の容量が減少して心拍出量が減少したり、拡張機能障害が起こることで、心臓がうまく血液を送り出せなくなり、最悪の場合、うっ血性心不全(CHF)や動脈血栓塞栓症(ATE)などの危険な状態となります。簡単にいうと『心臓が全身に血を送るのが下手になっている』ということです。
◯どんな症状があるの?
この病気は『心臓が全身に血を送るのが下手になっている』といことで、様々なことが起こっていきます。
・ 呼吸が速くなる:心臓が血液をうまく送り出せなくなることから、肺に送った血液がうまく心臓に戻ってこられず、胸水が溜まり、肺が十分に膨らめなくなったり、肺水腫といって肺自体に水が滲み出てしまうことから、十分にガス交換ができなくなり、普段よりも呼吸が速くなったり、息切れをしている様子が見られることがあります。血液の流れが悪くなっている状態を「うっ血」といい、心臓のポンプとしての機能が破綻している状態を「心不全」といいます。冒頭で触れた「うっ血性心不全(CHF)」とは、心臓がポンプとしての機能を十分に果たせなくなることで、血流が渋滞してしまうことをいいます。CHFを呈した猫ちゃんは命に関わる危険な状態になることがあるため、注意が必要です。
・お腹が膨らんでくる:心臓が血液をうまく送り出せなくなることから、心臓に血液を戻してくるということも下手になっており、腹水がたまることがあります。多少の腹水貯留は体調に大きく影響を及ぼすことはそれほどありませんが、腹水量が増えていくことで、胃腸の動きの低下や不快感から、食欲不振や元気消失が出ることがあります。肝、腎うっ血から、肝数値・腎数値の上昇、肝・腎機能の低下が起こることもあります。また、腹水によって横隔膜が胸側に押されてしまうために、呼吸がしづらくなることがあります。状況によって、肺や胸よりもお腹に腹水が溜まる猫ちゃんもいます。普段よりお腹がぽっこりしていて、急な体重変化があった場合は注意が必要です。
・突然の失神:心臓が血液をうまく送り出せなくなることから、脳へ十分に酸素が届かなくなり、突然気を失ってしまうことがあります。また、肥大型心筋症の猫ちゃんは不整脈も誘発されやすいため、ただでさえ拍出量が落ちている心臓に不整脈が発生することで、血液を送る効率がより下がり、失神へとつながることがあります。
要するに極端な話をすると、「呼吸の速い、元気のない、気を失うことがある猫ちゃん」になるということです。一概にこのような猫ちゃんが全てCHFを呈しているというわけではありません。すべての症状が出るというわけでもないため、気になることがあれば一度受診をお勧めいたします。
・後ろ足が動かない・突然暴れる:心臓が血液をうまく送り出せなくなることから、心臓の中でも血流のうっ滞が起こります。血液は流れが悪くなると固まりやすくなる性質があるため、肥大型心筋症の猫ちゃんの心臓には血栓ができやすくなります。この血栓が心臓から流れ出てしまい、動脈につまってしまうことがあります。これが、冒頭で触れた「動脈血栓塞栓症」です。猫ちゃんの場合、この血栓の塞栓が、後ろ足に血液を送っている大腿動脈に起こりやすいため、血流を失った後ろ足は麻痺していきます。また激しい痛みを伴うことがあるため、突然暴れ回ることがあります。少々過激な表現ですが、「のたうち回る」という表現が正しいかもしれません。
◯どうしてなるの?
猫ちゃんの肥大型心筋症の原因は、残念ながら完全にはわかっていません。遺伝的な要因が大きいと言われており、特に、メインクーンやラグドールなどの特定の品種の猫ちゃんは、リスクが高いとされています。また、腎不全を始めとする高血圧疾患、甲状腺機能亢進症などによって、二次的(続発的)に心筋の肥大が起こることもあり、“あたかも”肥大型心筋症のような状態に心臓がなってしまうことがあります。真の肥大型心筋症ではないものの、起こりうることが肥大型心筋症と類似するため、肥大型心筋症フェノタイプといわれています。
◯どうやって診断するの?
心臓の超音波検査での心臓の構造や機能評価、X線検査での心サイズの評価・肺野や胸水の評価、心電図検査での不整脈の有無、血液検査での基礎疾患の有無や心筋マーカーの評価、血圧測定での高血圧の有無から、状況を多角的に判断することで診断がつきます。
病理解剖でも確定診断とされるのですが、臨床的な肥大型心筋症の診断基準は「甲状腺機能亢進症、全身性高血圧などの基礎疾患または大動脈狭窄症の存在なしに心臓エコー検査にて拡張末期の左室壁厚が6mm以上となること」といわれています。心臓エコー検査において、左室心筋壁厚が6mmを超えてきた場合、基礎疾患を検査し、真のものなのか、フェノタイプなのか見定めていくイメージです。
◯肥大型心筋症かもといわれた…どうする?
怖いことをたくさん書いてきましたが、実はこの病気の猫ちゃんたち、ほとんどが元気に過ごしています。少し一安心なのですが、この病気の難しいところは、そこにあります。症状のない肥大型心筋症の状態を「無症候性肥大型心筋症」といいます。
2018年に世界21カ国にわたる多施設共同による「無症候性肥大型心筋症の猫群と見た目は健康そうに見える猫群の長期的な心血管リスクの評価」を目的とした後ろ向き研究が行われました。
無症候性肥大型心筋症(HCM/HOCM)群(1,008匹)のうち:
-
- CHF(うっ血性心不全)やATE(動脈血栓塞栓症)、またはその両方を発症したのは30.5%。
- 心血管系死(心臓関連死亡)は27.9%に達した 。
発症リスク(無症候性肥大型心筋症群):
-
- 1年後:CHF 7.0%、ATE 3.5%、心血管死 6.7%
- 5年後:CHF 19.9%、ATE 9.7%、心血管死 22.8%
- 10年後:CHF 23.9%、ATE 11.3%、心血管死 28.3% 。
・心血管合併症が発生した猫の平均生存期間は約1.3±1.7年で、予後は比較的短い 。
・無症候性肥大型心筋症群のうち、長生きしたのは一部で、9〜15年生存した猫は10%にとどまる 。
・健康猫(AH群)における心血管死のリスクは1%に過ぎなかった 。
☆『無症候性肥大型心筋症は世界的に重要な猫の健康問題であり、無症状であっても、CHF、ATE、心血管死といった重篤なリスクが高い』
といった結論に至っています。少し怖い結果ですね汗
元気に過ごしている猫ちゃんでも「実は心臓が悪かった、その結果、突然苦しくなった。突然血栓が詰まり、後ろ足が動かなくなった」が起こるということです。ただ、無症候性の肥大型心筋症の中央生存率自体は約11年というふうにも書かれており、その予後は概ね良好とも捉えることもできます。
「世界的な研究の文献を引っ張り出してきて、またまた先生、大袈裟な話をしてるんでしょ!」と思われる方もいらっしゃるといるかもしれません。残念ですが、意外と日常的に出会う疾患なのが現状です。循環器疾患は、早期発見することで注意深くその経過を観察し、早期に治療を行うことで、予後が期待できる場合があります。
残暑厳しい今日この頃、皆様の猫ちゃんはいかがお過ごしですか?当院では毎年、秋の健康診断を実施し、普段より健康診断を強化しております。その際、循環器についても健診を承ることが可能です。このブログを読んで「うちの子、大丈夫かな?」と思った方はお気軽にご相談ください。
猫ちゃんの健康を守るために、日頃からの観察が大切です。何か気になることがあれば、いつでも相談してくださいね。皆様の猫ちゃんが元気で幸せに過ごせるよう、私たちもサポートさせて頂きます。